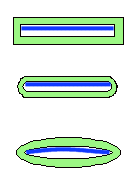| 13 | ウインドウェイを作ります。 これからがオカリナ作りの中で基本になるところです。 ウインドウェイ用のへらで先程開けた穴に向けてへらを差し込んでいきます。 このとき、差込スピードはゆっくり少しずつ入れて出し、出しては入れながら、少しずつ奥へ入れていきます。 |
|||
| 14 | へらが穴から顔を出したときの深さは約2〜5mmくらいが丁度良いようです(2mmから最高でも5mmまでです)どちらかというと2mm程度のほうが高音がきれいに出ます。 この作業はなるべく水を使用しないで行ってください。へらを少し差し込んで出しては、粘土のカスを水で洗っては水を拭き取り、なるべく水をウインドウェイに残さないのが後で良い音が出るかどうかのカギになります。 |
|||
| 15 | ウインドウェイのへらは竹から作ります。 鱒寿司の上下についてくる竹がぴったりです。 下の写真は鱒寿司を購入して集めた竹へら 未切削のもの |
|||
| 16 | 上左の赤丸の部分の寸法 アルトF管のウインドウェイへらの寸法 角型唄口の寸法を載せている。 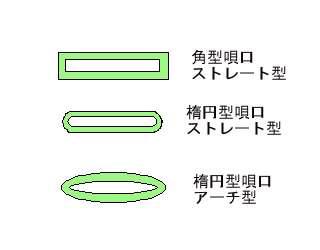 いろいろ試していますが、楕円型唄口アーチ型が一番良い音が出るような気もします。 |
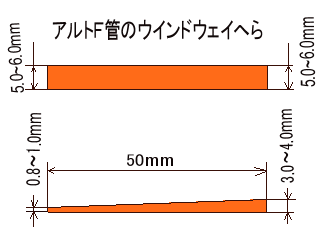 |
||
| 17 | へらを横からみたところ | |||
| 18 | へらが穴から覗いたら、かき出しへらでラビュームの広がりをかき出す。 赤の部分がラビュームの広がり. 赤の部分をかき出す 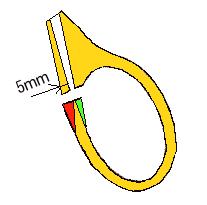 |
|||
| 19 | ラビュームの広がりはこんな感じ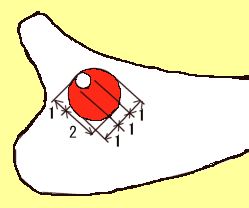 |
|||
| 20 | いよいよ中型を取り出すために二つ割にします。 このとき糸を使用して二つ割にする方法がきれいにできますが、長いへらやカッターで線を入れてもきれいに二つ割にできます。この方が楽です。 |
|||
| 21 | 二つ割にしたところ 中型は取り外し、中のティッシュペーパーはきれいに剥がす。 |
|||
| 22 | 右写真のように穴の奥に段をつけるため、かきへらで適量かき出します。 | |||
| 23 | 穴をつぶさないようにしながら、内側のラビュームの広がりをかき出します。緑色の部分が内側のラビュームの広がりです。 |
|||
| 24 | 内側のラビュームの広がり 赤と緑のラビュームの広がりをかき出したとき、残りの粘土の黄色の部分が、ウインドウェイのほぼ中心に来るようにすること。これが一番大事です。 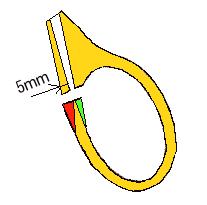 23 23 |
|||
| 25 | ラビュームの先のエッジを作る。 下図のように親指と人さし指でへらに沿ってこするようにして整える。 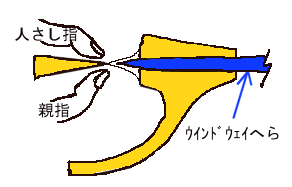 |
|||
| 26 | エッジの位置
|
|||
| 27 | 完成した片側 |